【女性中小企業診断士のAIO/LLMO実験🧩】AIに好かれる発信とは?──SEO構造が“伝わる力”に変わる理由
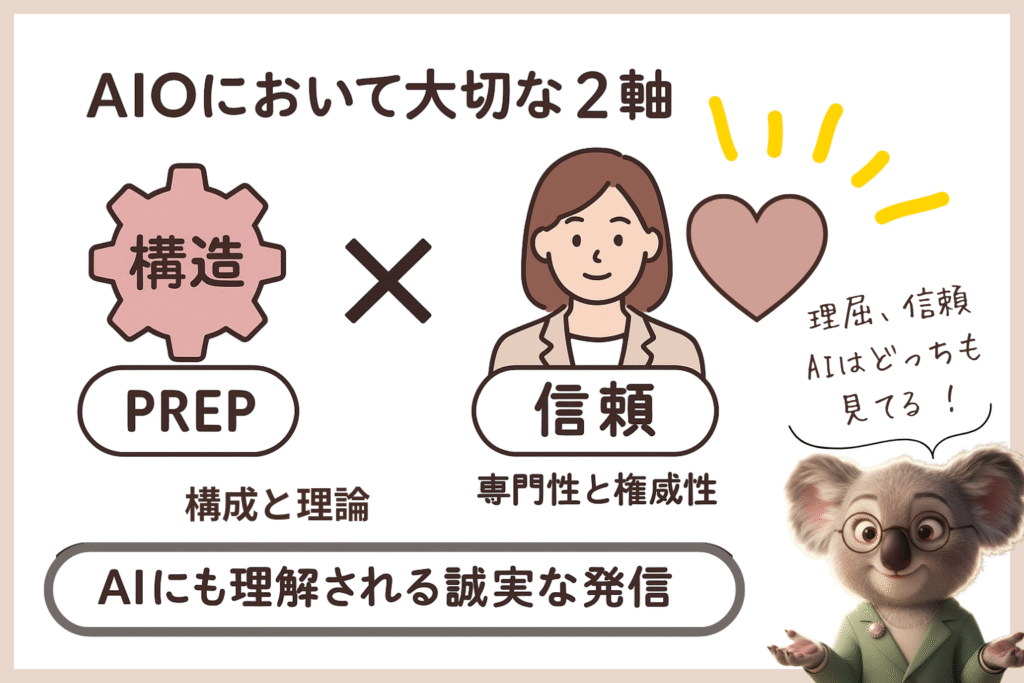
SEOとAIO(LLMO)、何が同じ?何が違う?
こんにちは、東京・多摩で活動する、女性中小企業診断士のはるこです🌸
最近ちょっと不思議なことがありました。
Google検索で「女性 中小企業診断士」で上位に来ていた私のブログ記事が、
ChatGPTやGeminiのAI検索でも引用候補として出てくるようになったんです。

「あれ?AIにも見つけてもらえるようになったの?」
と驚いて調べてみたら、そこにはちゃんとした理由がありました。
それは、SEOで意識していた“人に伝わる構造”が、
AIにも理解されやすい構造だったということ。
この記事では、
PREP法で整えた記事がなぜAIにも評価されたのか、
そしてSEOからAIO(AI最適化)へとつながる「構造」と「信頼」の2つの視点について、
実体験を交えてお話しします。
ハルコアラ先生、そもそもSEOとAIO(LLMO)って、どう違うんですか?
どっちも“検索に強くなる”っていう話には聞こえるけど…ハルコアラ先生 いい質問ですね!
SEOは“Googleなどの検索エンジン”に最適化する。
一方AIOは、“AI(ChatGPTやGeminiなど)”に理解・引用されやすいように最適化するんです。なるほど…!
じゃあ、SEOが“見つけてもらう技術”なら、AIOは“信頼してもらう技術”みたいな感じですかね。ハルコアラ先生 その表現、すばらしい✨
AIは“どんな言葉で”“どんな専門家が”“どう語っているか”を読み取ります。
ハルコさんも専門家としての経験や情報を、どう構造化して発信していくかがカギになってきますよ。
📖 目次
💡結論(Point):SEOで作る“人にわかりやすい構造”は、AIにも理解されやすい。だからこそ「伝わる構成」で書くことが大切。
なぜAIにも認識されるようになったのか…。
それはズバリ!
SEOで整えた“人にわかりやすい構造”が、
そのままAIにも理解されやすい構造だったから。
つまり、SEO対策をしっかりやっていたことが、
結果的にAIO(AI最適化)にもつながっていたんです。
なぜAIにも認識されるようになったのか…
最初は偶然かと思ったけど、実は“構造”だったんですね。ハルコアラ先生 そうなんです!SEOで整えていた“人にわかりやすい構造”こそが、
そのままAIにとっても“理解しやすい構造”になっていたんです。つまり、SEOで文章を“読者に伝わる形”に整えていたことが、
結果的にAIO(AI最適化)にもつながっていたんですね!ハルコアラ先生 そのとおり!
だからこそ、SEOもAIOも“別のテクニック”じゃなく、“同じ本質の延長線上”なんです。
どちらも“どうすれば相手(読者・AI)が理解しやすいか”を考える思考法なんですよね。
🧩理由(Reason):AIが読み取る「文脈と意味構造」とはどういうこと?
AIは今、単にキーワードではなく、
「文脈と意味構造」を読み取って回答をつくるようになっています。
特にChatGPTやGeminiなどのLLM(大規模言語モデル)は、
・見出し構造(H2/H3)
・箇条書き
・質問→回答の明確さ
・著者の専門性や一次情報
を重視します。
つまりブログがSEOで上がっている理由(=構造化・明確化・専門性)は、
そのままAIにとっても「読みやすい・信頼しやすい」条件なんです。
つまり──
SEOを丁寧にやるほど、AIにも好かれる。
これが今のAIOの核心です。
たしかに、“構造を整える”ってSEOでも大切ですよね。
でも、それがAIにも伝わるっていうのはちょっと意外です。ハルコアラ先生 そう感じますよね。
でもAIは、“読者に伝わる文章”をそのまま“理解できる構造”として評価しているんです。
たとえば、質問→結論→理由→具体例の流れ(PREP法)などは、特にAIには読みやすいと言われています。なるほど。
じゃあ、私のブログがAIに引用され始めたのは、
SEOで意識していた“読みやすさ”が効いていたからかもしれませんね。ハルコアラ先生 まさにそう。
SEOを丁寧にやるほど、AIにも好かれる。
これが、今のAIO(AI最適化)の核心なんです。
🧠具体例(Example):例えばこのブログは「PREP法」で書いている。
たとえば、私のこのブログでは、
「女性 中小企業診断士」というキーワードを中心に、
自己紹介や支援事例を PREP法(結論→理由→具体例→まとめ) の構成で書いています。
このPREP法で整理することで、
文章全体の“論理のつながり”が明確になり、
読者にもAIにも「主張と根拠の関係」が伝わりやすくなります。
つまり、AIは単にキーワードを拾うのではなく、
「主張→理由→実例→結論」の筋道がある文章を“理解できる構造”として評価しているのです。
💡PREP法とは?
P(Point)=結論
R(Reason)=理由
E(Example)=具体例
P(Point)=まとめ
💬実際のPREP例(この記事の場合)
P: SEOで上がった記事がAIにも拾われたのは、構造がAIに理解されやすかったから。
R: AIは意味構造(質問→答え、論理の流れ)を重視するため、PREP構成は効果的。
E: 「女性中小企業診断士」記事でPREPを使った結果、AI検索でも引用され始めた。
P: だから、SEO×PREP=AIOにも強い発信になる。
こうして見ると、PREP法ってシンプルだけど、
ちゃんと“筋道を立てて話す”仕組みなんですね。ハルコアラ先生 そうなんです。
AIは“何を言いたいのか?”“その根拠は何か?”という
構造を理解して文章の信頼性を判断しています。
だからPREP法で整理された文章は、人にもAIにも伝わりやすいんですよ。なるほど。
つまりPREP法は“伝えるための型”であると同時に、
AIにも好かれる“理解される型”なんですね。ハルコアラ先生 まさにその通り✨
結局、人に伝わる文章はAIにも伝わる。
PREP法は、それを自然に実現できる“橋渡しの構造”なんです。
🧭もう1つ大切なのは、AIに“信頼される専門家”になること──AIO的発信の次の一歩
ここまでお話ししてきた「PREP法」などは、AIに理解される“構造”を整えるための方法でした。
けれど、AIO(AI最適化)にはもう一つ大事な要素があります。
それは、AIに“信頼される専門家”として見せること。
AIは、文章の中身だけでなく、
「誰が書いているのか」「どんな分野の専門家なのか」も読み取って判断しています。
つまり、これからは“構造”だけでなく“文脈上の信頼性”も設計することが必要です。
ここからは、専門家としてAIにも伝わるための
「見せ方」「発信設計」について見ていきましょう🌸
🧠AIOで重要な“信頼の設計”3つの視点
① タイトルを「質問+専門性」で設計する
AIは“質問と回答”のペアを認識しやすく、回答の根拠として引用しやすい。
たとえば:
「女性中小企業診断士ブログがAIに引用される理由とは?」
「SEOで上位の記事が、AIにも拾われるのはなぜ?」
「質問型+専門性」を入れるだけで、
AIが“どんな疑問に答える記事か”を正確に把握しやすくなります。
② 専門家プロフィールを明示する
AIは“誰が発信しているか”を信頼判断に使います。
以下の3点を整えると、AIにも人にも「信頼できる発信者」として見てもらえます。
- 職業・資格・活動地域(例:「東京都多摩地域で活動する女性中小企業診断士」)
- 実績(例:「創業支援200件以上」「商工会・大学講師経験」など)
- 著者ページや署名欄の整備(発信者が明確)
これらは単なるプロフィールではなく、
AIにとっての「信頼の証明書」になります。
③ FAQやシリーズ化で“サイト全体の文脈”を作る
AIは単一の記事よりも、「テーマの一貫性」や「全体のつながり」を評価します。
そのため、関連テーマをシリーズ化したり、FAQでまとめたりするのが効果的です。
例:
「SEO実験🧪」→「MEO🗺️」→「AIO🤖」のように連動させる。
こうすることで、
AIはサイト全体を“専門家ハブ”として理解し、
読者にも「体系的で信頼できる発信」として伝わります。
SEOの重要な考え方に、E-E-A-Tがあったと思います。
やっぱりAIOの“信頼”って、E-E-A-Tのことなんですか?ハルコアラ先生 とても近い考え方です。でも、方向がちょっと違うんです。
E-E-A-Tは“Googleに評価される信頼性”。
AIOは“AIに理解される誠実さ”といった感じですね。あ、なるほど。
Googleは“他人があなたをどう見ているか”を評価するけど、AIは“あなたの文章の中身と一貫性”を読む、ということでしょうか。ハルコアラ先生 その通り。AIOでは、“構造を整え、プロフィールで誠実に自分を見せる”ことが大事。
AIはリンクよりも“文章の中の文脈”を信用するんです。
E-E-A-Tが“外からの信頼構築”なら、AIOは“中から伝わる信頼設計”のイメージですね。
🌷まとめ(Point)
SEOとAIOは別物のように見えて、
“伝わる構造をつくる”という点では同じ方向を向いている。
AIは「誰が・どんな根拠で・どう伝えているか」を読む時代。
だからこそ、専門家としての体験や考え方を、
PREP法で整えていくことがいちばんのAIO対策です🌸
💬結論:
つまり「SEOで上がった記事がAIでも拾われた」のは偶然ではなく、
- 明確な構造(PREP)
- 見出しや文脈の整理
- 専門家としての信頼性(E-E-A-T)
この3つが揃っていたから。
これらはAIが“回答の根拠に使える記事”を選ぶ条件に一致しているため、
ブログのSEO努力がそのままAIOにも効いていた、という理屈でした💡
🧸最後のひとこと
-scaled.jpg)
AIOの結論って、結局のところ“AIのためのSEO”じゃなく、“AIにも伝わる人間らしい文章術”なんですね。
ますます人間の評価に近づいてきた気がします。

そうなんです。
結局、誠実にわかりやすく書く人がいちばん強い。
それは人間でもAIの世界でも変わらないのですね。
💬 無料で相談・学びたい方へ
SEOやAIOの整え方を実践したい方、
「構造」と「信頼」を記事に落とし込みたい方は、
下のフォームまたはLINEからお気軽にご相談ください🌸
👩🏫 この記事を書いた人
伊藤明子(はるこ)
女性中小企業診断士・ITコーディネータ|RASHIKU Consulting 代表
東京・多摩を拠点に、起業支援・Web活用・地域密着の事業伴走を行う。
「ありがとうでつながる起業」をテーマに、女性起業家のWeb発信を支援中。

お気軽にお問い合わせください。また、LINEからも最新情報やセミナー案内をお届けしています。
ぜひご登録ください✨


